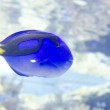麦湯の女—横浜・居留地と盛り場のダイナミズム
1.伊勢佐木町・ニューテアトルの閉館
横浜・伊勢佐木町の「横浜ニューテアトル」がこの6月1日をもって閉館した。最後に上映されたのは、同地で名を馳せた岡山出身の娼婦・メリーさん(1921年―2005年)を追ったドキュメンタリー作品『ヨコハマメリー』(中村高寛監督作品・2006年)だった。
横浜ニューテアトルの前身は、1955年4月に開館した東京テアトル系「テアトル横浜」。1972年に長谷川重行氏が買い取り「横浜ニューテアトル」と改称して営業を続け、1996年からは重行氏の子息・喜行氏が経営を引き継いでいだが、経営不振とオーナーの健康問題から閉館を決めたという。
伊勢佐木町の賑わいは1880年頃に始まったといわれる。明治維新からわずか12年しか経っていないが、賑わいのの起源を遡れば1859年7月1日(安政6年6月2日)の横浜開港に突き当たる。
2.居留地をめぐる「欲」と「騙しあい」
開港前の「横浜村」は人口数百人。地域の大半は海か沼で、人びとは半農半漁で慎ましく暮らしていた。首都・江戸からの街道(東海道)に通ずるまともな道もなく、隣村の宿場町・神奈川との交通も、船を繰りだすか山越えをするかという有様。伊勢佐木町は田でも畑でもない、たんなる沼地だった。
『一外交官の見た明治維新』(1921年)で有名な英国の外交官・アーネスト・サトウによれば、「商売に無知な山師」であり「不正直者」である日本人と、サトウの上司でもあった初代英国総領事・オールコックによって「ヨーロッパの掃き溜め」と名づけられた居留地に住む人品骨柄の怪しき英国人、米国人、フランス人、オランダ人や、彼らが上海や香港から使用人として連れてきた中国人とが、生まれたばかりの貿易港湾都市・横浜の主役だった。
後に関外地区のヘソとなる伊勢佐木町が盛り場としての土台を整え始めたのは1870年、明治3年のことだという。この年、居留地に隣接する大岡川以南の埋め立てが許可され、一部については地固めする作業も始まったが、『横濱沿革誌』(大田久好・明治25年=1892年)には次のような記述がある。
明治三年五月。吉田橋脇ヨリ入船町野毛浦迄埋立竣功、之ヲ新街道ト云。受負人真砂町(京屋)内田清七、入船町ヨリ野毛浦埋立地地固メノ為メ、葭簀張(よしずばり)納涼茶屋、其他軽業、辻講釈、昔噺等ノ興行ヲ神奈川県裁判所二出願、許可ヲ得テ興行ス。・・・ 爾来、納涼遊歩者日々群ヲ成シ、麦湯店ノ流行殆ンド埋立地ノ過半ヲ占ムルニ至レリ
太田久好著『横浜沿革誌』1892年(139-140頁)
この資料には、同年6月10日に、野毛山沿岸に浮かべた小舟から100発の花火を打ち上げ、人を集めて埋め立て竣工を祝った様子も描かれている。物見遊山の客を多数呼びこみ、彼らの足に頼って地固めをしたとはなかなかの知恵である。興業の上がりもそれなりに得られただろうから、地ならしと経費捻出の双方を満たす一石二鳥の奇策であった。「葭簀張(よしずばり)納涼茶屋」が気になるところだが、これは最後の一文にある「麦湯屋」のことを指している。当時の麦湯屋の実情については本稿末尾であらためて触れてみたい。
3.遊廓と盛り場のダイナミズム
港崎遊廓は、錦絵、講談、芝居などで有名な岩亀楼を頂点に絢爛たる遊郭として賑わったが、1866(慶應2)年10月20日の大火(通称・豚屋火事/死者400人超)で焼失してしまう。焼失した遊廓の跡地はやがて日本初の西洋式公園である横浜公園に姿を変えることになるが(1875年)、遊廓はその後、吉田橋南方吉田新町に仮移転、翌1867(慶應3)年、吉田新田の一部(現在の羽衣町周辺)を埋め立ててあらたなスタートを切る。このとき「港崎遊廓」は江戸の吉原に倣って「吉原遊郭」に改称されている。
この吉原遊廓も開業4年後の1871(明治4)年に再び火災を起こして焼失し、1872(明治5)年、高島町の埋め立て地に移転して「高島遊郭」として仕切り直すことになった。1871(明治4)年に開通した新橋=横浜間の鉄道路線に近接した場所に設置され、東京あたりからも遊客を集めて栄えたという。ところが、開業から8年も経った1879(明治12)年になって、「天皇や外国人が乗車することもある鉄道を見下ろす場所に遊廓があるのは怪しからん」と急に問題視されるようになり(実際には遊廓と線路のあいだには目隠しのための板塀が設置されていた)、県令(知事)から「遊廓を即刻取り払え」という命令が下された。その背景には、遊廓需要を当てこんで投機的に入手した土地を遊廓に使って欲しいと願う横浜・関外の地主たちによる、太政官(内閣)への猛烈な「陳情活動」があったらしい(『横浜開港側面史』明治42年=1909年・横浜貿易新報社・186-189頁)。
その結果、高島遊廓は直ちに閉鎖され、旧吉原遊廓周辺に仮移転した後、1880(明治13)年になって旧吉原遊廓から500メートルあまり西南西の指定地域に遊廓は移転を完了し、一帯は真金町・永楽町と命名された。遊廓は両町の頭の二文字をとって「永真遊廓」と呼ばれ、1958年の売春防止法施行まで生き残ることになった。なお、真金町は落語家・桂歌丸の生家だった遊女屋「富士楼」のあったところだが、椎名家(歌丸の本姓)のこの娼楼は、東京の吉原で引手茶屋(待合茶屋)を経営していた歌丸の祖父母が、関東大震災後真金町に移転して開業したもので、明治のこの時期にはまだ存在していない。
まもなく「遊興の街道」から外れた裏街道筋(黄金町など)にも、アンダーグラウンドな娼婦や博徒が集う「場末」が出現し、伊勢佐木町を中心とする「関外」は、早くも明治20年代に東京の浅草などと並んで日本を代表する盛り場に成長した。開港時わずか数百人だった「横浜村」の人口も、神奈川、保土ケ谷、戸塚といった周辺の宿場町を併せて市制の敷かれた1889(明治22)年には12万人まで膨張している。
日本に映画が輸入されたのは1896(明治29)年のことだが、横浜船渠で造船が始まった1897(明治29)年には、住吉町の芝居小屋「港座」で初の映画上映が行われ、1908(明治41)年になると横浜の映画館の第一号として伊勢佐木町に「喜音満(きねま)館」が開館している。1911年(明治44年)には賑町(現伊勢佐木町3丁目)に、日本最初の洋画専門館「オデヲン座」が開館するが、オデヲン座で使われた「封切」という言葉は、「新作映画の初上映」を意味する映画用語として定着した。伊勢佐木町がこの国を代表する映画館街・盛り場であったことの証である。
開港と同時に武蔵国の一寒村にすぎなかった沼沢地に、国内外から続々と人びとが集まり、さまざまな欲望と希望とが渦巻くなか、埋立てにつぐ埋立てが行われ、住居、工場、商店、芝居小屋・映画館、妓楼が次々に建てられていった。山を削るのも、海や沼を埋めるのも、水路を引くのも、建物を建てるのも、すべて人力で行うほかなかった時代に、わずか30年余りで都市が形成され、経済と文化の一大センターとなった。横浜あるいは伊勢佐木町の歩みを見ると、功成り名を遂げた人びとと名もなき人びとが、美徳と悪徳の大海をともに泳ぎ、時にはつぶし合い、時には助け合いながら、「お上」に頼るのではなく、市井の人びとが自分自身の手で自発的に、封建的な不自由を近代的な自由に造り替えた歴史の刻印であると思う。そこには、人間の偉大さと卑小さとがモザイクのように織りこまれている。レンガ造り、石造りの西洋建築や独特のエキゾティシズムばかりが注目される横浜の歴史だが、「人間のダイナミズム」を感じられる点にこそ横浜の歴史の魅力がある。
4.麦湯屋奇譚
横浜(あるいは伊勢佐木町)のダイナミズムを観察するなかで、妙に気になるのが「麦湯屋」の存在である。麦湯とは、いまでいう麦茶のことなのだが、江戸時代中盤以降、初夏から夏にかけての盛り場にはつきものの露店であったという。その態様は時代によって少しずつ異なるともいうが、うら若き女性が浴衣姿で鉄瓶や真鍮の薬缶などで沸かした熱い麦湯を給仕するのが基本的なサービスである。麦湯以外に甘酒や葛湯などのメニューもあったようだ。客の大半は男性で、よしず張りの露店の縁台に腰掛けてその麦湯をすすりながら給仕役の女性をからかう。ただそれだけの、どちらかといえば健全な「軽風俗」なのだが、夏の夕暮れから深夜にかけて、客は引きも切らなかったという。赤地に黒い文字で「むぎゆ」と書かれた縦提灯をぶらさげた闇夜の露店を見かけると、居ても立ってもいられなくなる御仁も多かったという。
 江戸時代の江戸の町では、麦湯屋が夜の裏街道を占拠するほどの隆盛をきわめた時期もあり、幕府が規制に乗りだしたこともあったが、お触れのほとぼりが冷める頃合いを見計らって、麦湯屋は雨後の竹の子のごとく繰り返し出現したという。それだけ根強い人気があったのだろうが、開港後の横浜でも、夏の夜の盛り場は麦湯屋で埋め尽くされ、その人気は大正時代まで続いたという。明治初期、旧幣制下の横浜では「24文」が相場だったらしいが、かけそばが16文だったので、今でいえば700〜800円とちょっと高めの喫茶店価格。こうした絶妙な値段設定も客の心をくすぐったことだろう。
江戸時代の江戸の町では、麦湯屋が夜の裏街道を占拠するほどの隆盛をきわめた時期もあり、幕府が規制に乗りだしたこともあったが、お触れのほとぼりが冷める頃合いを見計らって、麦湯屋は雨後の竹の子のごとく繰り返し出現したという。それだけ根強い人気があったのだろうが、開港後の横浜でも、夏の夜の盛り場は麦湯屋で埋め尽くされ、その人気は大正時代まで続いたという。明治初期、旧幣制下の横浜では「24文」が相場だったらしいが、かけそばが16文だったので、今でいえば700〜800円とちょっと高めの喫茶店価格。こうした絶妙な値段設定も客の心をくすぐったことだろう。
どちらかといえば「健全な風俗」だったはずの麦湯屋だが、実際には怪しげな店舗も多かったようだ。以下は『横浜開港側面史』(前掲書、218頁―220頁)からの抜粋である。
(麦湯屋には)二十二、三ぐらいの新造(しんぞ)と、他に十三、四の女童(おなご)、又は三十四、五ぐらいから四十五、六ぐらいの女が居て、麦湯・葛湯などを拵(こしら)えて出す。新造が給仕をする、客の接待をする、客を呼びこむと云うふうで御座いました。又市中の若殿原、さては職人などは夕食をしまうと麦湯素見(むぎゆひやかし)に出かけます。呼びこまれて縁台に腰を下ろす。新造は『あなた何を上げます』と聞く、麦湯一杯下さいと云う、この面に於いて客は女に注目し女は客に注目し、相互の意気投合すれば、忽(たちま)ち一種の情約成立し、女は『おばさんわたし鳥渡(ちょっと)家に行ってきますよ』と云って出かける。客は其跡(そのあと)に随(つ)いて魔窟に入り、魔風を吹かせて店へ帰るを先ず普通とし、特別条約として、一時頃店をしまう頃に来て、女を携えて魔窟に入り翌朝まで魔術を弄するそうです。斯有(かかる)手段に至っては千変万化で、今も昔も異なることはありませんですから明治五年には麦湯営業の許可をしない事になりました※7
『横浜開港側面史』横浜貿易新報社 編 1909年(218頁―220頁)
すでに欧米諸国との「不平等条約」が市中で話題になっていたと見えて、「情約」や「特別条約」という言葉が使われているところになんとも滑稽の趣があるが、「魔窟」という穏やかならぬ表現も気になる。おそらくは近所の貸間のことでも指すのだろうが、麦湯屋が表看板だけで、実体はちょんの間(簡易な売春宿)だったところもあったのだろう。他の資料を見ると「麦湯を飲んで女性をからかって帰る」のが麦湯屋との正しい付き合い方であって、それ以上を求めるのは「無粋」という風潮も強かったようだから、売春麦湯屋は一部に限られていたのだろう。なお、「明治5年に麦湯屋は禁止された」とあるが、明治7年には麦湯屋に鑑札料を課して許可したという記録もあるから、いったんは「禁止」したものの、当局は「登録して手数料を払えば許可」という方針に転換したものと推定できる。
ひょっとすると、現代においても麦湯屋に類推できるものはあるのかもしれないが、上記の資料が示すような生き生きとした描写に接すると、この時代の「庶民のバイタリティ」には驚くばかりである。現代の「品性」はもはや麦湯屋を許容しないだろうが、品性を得ることによって失われた「底力」のようなものが存在したことだけは記憶に留めておきたい。
横浜の記事いろいろあります→ 横浜、山下町あたりの記事 を見てみる