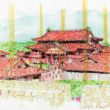続・杉本文楽と沖縄独立〜日琉同祖論と日琉異質論
杉本文楽をめぐる前稿のなかで、日琉同祖論と日琉異質論について触れたが、これについては若干補っておく必要があるだろう。
江戸時代から今日にいたるまで、「日本と琉球(沖縄)は先祖を同じくするから、歴史的・民族的アイデンティティを共有する」という主張= 日琉同祖論 と、「そうではない、日本と沖縄は一部の歴史が重なり合うだけで、それぞれが独立した歴史的・民族的アイデンティティを有する」という主張=日琉異質論があり、対立を繰り返してきた。
杉本博司の指摘の通り、「1万年もつづいた縄文時代」が日本人のアイデンティティの根っ子にあるという前提で考えると、縄文時代を、少なくとも日本と同じようなかたちで共有しない沖縄の歴史的・民族的 DNA、あるいは文化的DNAは、日本のそれとは異なる可能性が高くなる。結果として、異質論に加勢する主張で、今後出てくるかもしれない新しい沖縄独立論のひとつの根拠となりうる。
だが、ぼくはそうは思わない。「縄文時代が1万年続いた」という杉本博司の想定に関わる文化的な展開に疑問を呈するわけではない。歴史を遡って俯瞰すれば、1609年の薩摩侵攻以来、日本と沖縄は歴史を一 体的に共有するプロセスを歩んできたことは否定しようもない、という点を強調したいのだ。
それが薩摩側の武力という強制力によるものであろうが、琉球側の、生き残りを賭けたしたたかな外交戦略によるものであろうがまったく無関係である。日本と沖縄が一体化に向かう歴史の激流に、誰も抗しきれなかったということである。
たしかに薩摩が3000名からなる兵力で沖縄をねじ伏せた薩摩侵攻は沖縄にとって忌むべき「侵略」だったろう。王国が一夜にして消滅し、日本のなかのたんなる一地方として再編成された琉球処分(1879年)も大いなる屈辱だったろう。その琉球処分から66年後の沖縄戦で被った被害も未曾有のものだったろう。だが、これらの厳然たる歴史的事実を「沖縄を平気で犠牲にしてきた日本の暴虐」と位置づけようとすることは、歴史の非情さを責めることと等価である。もっといえば、どうあがいても変えられない過去を変えようとする虚しい試みに等しい。
薩摩侵攻も琉球処分も沖縄戦も、すべて複合的な要素によって起こった悲劇である。
たとえば薩摩侵攻。秀吉の朝鮮出兵への助力要求に十分こたえなかった琉球王府の姿勢がその端緒だといわれているが、明の冊封国・朝貢国に留まるか、日本への従属関係を選ぶかという二者択一に直面して、揺らぎながらも明を選ぶかたちになったのは王府独自の判断であった。その判断を前提に、薩摩は幕府の許可を得て琉球をわがものにしようと目論んだのである。幕 府や薩摩の厳しい対応をみて、武力制圧も十分ありうると事前に予測することは可能だったはずだが、この点で王府は明らかな判断ミスを犯し、やすやすと蹂躙されてしまう。こうした歴史的経緯を「暴虐な日本(薩摩)と哀れな琉球」という構図で片づけ、日本の責を問うのは簡単だが、政治・外交史上の事実を捉えて 「犯人は誰だ!」と叫ぶことにどれほどの意義があるのだろうか。あえて犯人を捜せというなら、王家や行政府の長である三司官(幕府の老中に相当)も同罪である。
琉球はその後も形式的には独立国として存続するが、 実質的には薩摩(幕府)の属国であった。琉明貿易での利益を当てこんだ薩摩にとって、琉明関係が崩れてしまっては元も子もない。また、小国とはいえ明という大国に朝貢する一王国を従属させることで、薩摩藩は他藩に対する優位性も確保できる。キリスト教排除を主目的とした鎖国政策を推し進める幕府にとって も、外国との繋がりが維持できる飛び石外交・飛び石貿易的なシステムは都合がいい。だからこそ琉球は独立国として存続できたのである。が、「もっぱら日本側の事情で琉球は独立国として存続した」のではない。琉球あるいは尚王朝にとっても少なからぬ利点があったからこそ、維持できるシステムだったのである。 琉球王朝の側も、折に触れて明(あるいは清)との関係をアピールし、「われわれを存続させることは日本にとって大きな利益となりますよ」という宣伝を怠らなかった。
侵攻に成功した薩摩だが、制圧後、琉球支配のために常駐させた役人はわずかに十数名。彼らは現在の那覇市東町の交差点あたりにあった在番奉行所(または御仮屋ウカリヤ)で仕事をしていたというが、首里城への出入りも禁止されており、情報収集と武器の管理(薩摩侵攻を契機に王府は武装解除され、全島から集められた武器・武具は、すべて在番奉行所の管理下に置 かれた)ぐらいしか仕事はなかったようだ。実際、ほとんどの政治的・外交的意思決定は、鹿児島にあった琉球館で行われていたという。鹿児島の琉球館には王府から派遣された役人が十名余り勤務していたが、薩摩藩の役人も同館に詰め、問題が起こると両者で協議した。つまり、薩摩による支配はきわめて緩やかで、 内政について深く干渉することはほとんどなかったといわれている。その意味では自治国だったのである。
この程度の支配関係だったから、沖縄に在する帰化人・中国人や王府内の中国派が、中国(明や清)の軍事力・政治力をバックに一致結束すれば、沖縄から薩摩藩を追い出すことなど簡単にできたはずである。が、誰も決起しなかった。なぜか。そんなリスクを冒す必要がなかったからである。薩摩に従属し、中国に朝貢するという「二重支配体制」を甘受しさえすれば、生き残れたからである。
しばしば薩摩の支配は過酷だったといわれる。たしかに重税だったことはまちがいない。が、徴税面だけでなく、財政支出面まで詳しく検討すれば、「必ずしもそうとはいえない」という実態も浮かび上がってくる。資料が乏しいので明言はできないが、朝貢(王府代表者の訪中)や冊封(中国王朝代表者の来琉)といった外交行事が行われるたびに、薩摩側は相応の資金提供を余儀なくされた。支出の大半は貿易取引に要する資金提供、つまり王府に対する貸付金だった。
王府の役人は、薩摩から借り受けた資金を元手に中国 製品を仕入れ、これを薩摩や琉球の商人に売り渡すが、王府の手元には資金がないため、取引のたびに薩摩に借金していたのである。借金だから返済が義務だが、王府財政は年々悪化していたので容易に返せない。結果として薩摩藩に返済するために薩摩藩に借りることも珍しくなかったという。今でいえば借り換えである。「薩摩藩に返済するために薩摩の商人に借りる」こともあったようだ。 役人の中には個人的に資金を調達して中国製品を仕入れ、これを市場で売買して大もうけした者も少なからずいたようだが、これはあくまでも私的なレベルでの話。公的な収支レベルについていうと、琉明貿易・琉清貿易自体が赤字だったこともほぼ明らかになっている。
薩摩の立場からすれば、侵攻当初の思惑はすっかりはずれてしまったことになる。版図は広がったが負担は累増した、というのが薩摩による琉球支配の実態であったといえるだろう。琉球は薩摩にとって財政的にはお荷物だったのである。琉球側からみれば、政治的な従属という代価と引き換えに、財政的な援助という実利を得ていたことになる。それでもなお薩摩が琉球を 手放さなかったのは、中国に連なる「異国王朝」を支配していると強調することで、幕藩体制における相対的な優位性が確保できるからであった。その点では幕府も利害が一致していたのである。
薩摩や幕府にとって琉球は「異国」でなければメリットがなかった。だから、王朝からの使者に対しては、異国風を強調する髪型、衣装、アクセサリーなどを要求した。琉球の側もいやいや要求に応えていたわけではない。自らも異国であることを強調することによって、生き残りが容易となったからである。日本に対しても、中国に対しても、頼りのない独立国を装うこと によって外交的メリットや経済的メリットを最大限享受することができたからである。
1816年、イギリス海軍が来琉したときの王府の対応も基本的にこれと同じだが、ちょっとばかりバージョンアップしている。できうる限りのもてなしと礼節をもって臨み、「わが琉球は、人はよろしいがたいした資源もない貧しい国で侵略に価しない」と印象づけることで、ベイジル・ホールなどの指揮官を懐柔、彼らを40日で引き取らせることに成功している。われ われは中国派でも日本派でもない、武器も知らない貧しい民が南海の孤島で肩寄せ合って慎ましやかにくらしているのだ、などというおとぎ話を、当時のスーパーエリートであるイギリス海軍将校が信じたとは俄に思いにくいが、ベイジル・ホールはイギリスに帰還する途中、セント・ヘレナ島に幽閉されていたナポレ オン・ボナパルトに面会し、「世にも珍しい武器をもたない平和な国」として琉球を紹介している。
その理想的な平和国家・琉球は、薩摩(日本)に鎖をつながれながら、中国に尻尾を振っていた。
琉球はそれは本意ではなかったという。日本に威嚇され、仕方なく鎖に繋がれたのだという。中国は酷いことはしなかったのに、日本にはさんざんな目にあったという。中国は文化という財産を分け与えてくれたが、日本は暴力をふるうだけだったという。
これは王府内の中国派の考え方であって、今でもこれに繋がる考え方(日本批判)は根強い。中国は酷いことをしなかったというが、琉球に対する関心が薄かっただけ、というのが真相だろう。明治期に入ってからも、台湾ですら「化外の地」として中国の領土的野心の外側に置かれていたのだから、琉球に対する積極的関心があったとはとても思えない。
清の時代には、「そんなにしょっちゅう挨拶に来なくていいから」といわれたこともあるのだが、ここで切り捨てられたらお終いだと慌てふためいた琉球側は、「いやいや、そんな冷たいことおっしゃらず頻繁にお邪魔させて下さいよ」と繰り返し嘆願している。朝貢・冊封の関係は、琉球にとって経済的な生命線であると同時に、日本との政治的関係を維持するためにも不 可欠だったからである。中国との朝貢・冊封の関係がなければ、日本から切り捨てられるか、完全に植民化されるかのいずれかである。琉球にとってこれは最悪のシナリオだ。
中国派に対して、王府内の薩摩派(日本派)は、言語的にも文化的にも日本からの影響が大なることを認めた上で、日本との関係がなければ経済的に成り立たない、という現実路線を強調したが、それも日本からの有形無形の援助を当てこんでのことである。中国の傘下にあるよりも日本の傘下にあったほうが、得るものは大きいという判断である。琉球に「国体」というも のがあるとすれば、国体を売り渡すことになりかねない判断だから、中国派にとってこれは唾棄すべき選択ということになる。
実際の王府の政治は、中国派と日本派(薩摩派)のあいだで揺れ動きながら結果的に中庸を選ぶことが多かったようだが、これまで見てきたとおり、琉球の命運を直接左右するのは、実は中国との関係ではなく、日 本との関係だったことは明らかである。中国派は、政治的な観点から「日本との関係を維持するために」中国に切られるわけにはいかないと判断していた。日本 派は、経済的な観点から「日本に依存するほかない」と判断していた。いずれのベクトルも完全に日本に向いていたのである。
薩摩の侵攻が「正義」だったのか問われれば、蛮行だったというほかない。が、そのときどきの政治状況、経済状況、国際関係などのさまざまな要素が絡むことによって、いずれの国もいずれの民も、自分たちで制御できない方向に流されてしまうのが歴史の現実である。
1609年、琉球は薩摩(幕府)の版図に組み込まれると同時に中国の朝貢国としての地位も保つことになった。積極的な選択でなかったとしても、琉球は薩摩(日本)に依存するかたちでしか生きられなくなっ た。薩摩(日本)も琉球を取り込むことで多くのメリットを享受した。一種の相互依存関係が、薩摩による植民を回避させ、独立国・琉球を延命させることに なったのである。が、この日本に従属的な独立国の成立が、その後の琉球・沖縄の歩みを決定したのである。琉球処分も、実はその延長線上にある。
アジアにおける中国の冊封体制が完全に崩壊し、日中 の鎖国が解かれた19世紀後半以降、国際秩序はまったく別物となった。冊封体制と幕藩体制を外交の軸に据えて、ふらふらとバランスをとり、隙間を縫うように生きながらえてきた琉球の命運は、この時点で尽きてしまったといっていい。琉球処分に対する批判(明治政府批判・日本批判)は今でもかなり強い。批判者の心情もわからないことはない。が、当時の状況を勘案しながら明治政府の立場に立ってみれば、これ以外の判断はありえないと思えるほど、あらたな中央集権システムの下に琉球を組み込もうとする手法はまったく自然な判断であった。それが正義であるかどうかはわからないが、過去の経緯からいえば、誰もが予想しうる手法であった。
ところが、王府は過去の幻影に縛られ、明治政府の出方を正しく予想できなかった。それはミスとしかいいようがない。もっとも、王府が正しく予想していたとしても、結末は変えられなかったかもしれない。が、一縷だが、この時点で真の意味で独立する望みはあった。結果として王府はそれを選ばなかった。日本の庇護の下に、これまでの王朝の体制を存続できると楽観 的に評価していたからである。明らかな判断ミスだ。
琉球が日本と同祖なのか異質なのか、はたまた独立国としての資格をいまだ備えているのか、といった問題提起は興味深い。だが、普天間基地の移設問題が再び浮上する時期となり、歴史の流れを無視した議論がこれ以上展開されるのは、もはや耐えられない。沖縄異質論が「沖縄は特別」という議論にすり替えられ、「弱者が強者を打ち負かす」といった本質的でない部分 に光が当たるような事態だけは避けたい。
正直にいおう。あたりまえのことだが、沖縄は独立国ではない。沖縄だけが特別な近代史を歩んできたわけでもない。ここに至るまで、薩摩藩や幕府や明治政府や日本軍国主義は、沖縄に対して冷酷無比だったかもしれぬ。が、琉球・沖縄の王家・行政官・政治家たちもさんざんなミスを犯してきたのである。そのことを肝に銘じた上での歴史的な判断が、今望まれているの ではないか。
※画像は明治初年の那覇市街図の一部。中央部分に「在番奉行所」の位置が示されている。宮城栄昌・高宮廣衛(編)『沖縄歴史地図』(柏書房・1983年)より。