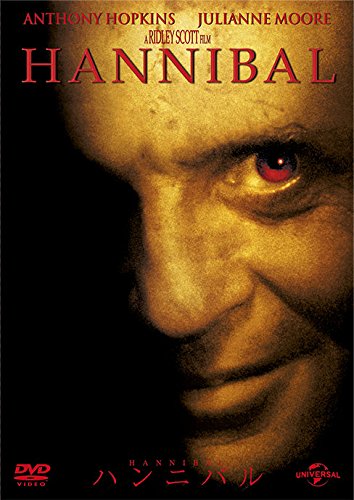龍涎香奇譚 —レクター博士、エイハブ船長、照屋林助
レクター博士の龍涎香
まずは映画『ハンニバル』(リドリー・スコット監督/2001年)の1シーンから。
調香師
「ハンドクリームですね、天然のアンバーグリスに、テネシーラベンダー、それから…羊毛、やっぱり羊毛です」クラリス
「アンバーグリス?」調香師
「アンバーグリスはクジラから採れる天然の希少香料です。残念ですが、我々アメリカでは絶滅危惧種法で輸入することはできません」クラリス
「合法的に入手できる国は?」調香師
「もちろん日本。それとヨーロッパでも。パリ、アムステルダム、ローマ。 あとはおそらくロンドン。この香りはオーダーで調合されたものです」クラリス
「入手可能なお店はわかりますか?」調香師
「 もちろん。店舗のリストをすぐに送りましょう」(以下原文)
Perfumer
– Hand cream…, Raw ambergris base, Tennessee lavender, Trace of something else…
– Fleece.
– Lovely.Clarice
– What’s ambergris?Perfumer
– Ambergris is a whale product. Alas, much as we’d like to, we can’t import it. Endangered Species Act.Clarice
– Where isn’t it illegal?Perfumer
– Japan, of course. Couple of places in Europe. You’d almost certainly find it somewhere in Paris…, Rome, Amsterdam.
– Maybe London.
– This bouquet was hand-engineered to someone’s specifications.Clarice Starling
– Is there a way of knowing which shops?Perfumer
– Of course. We’ll give you a list. It’ll be short.
ハンニバル・レクター博士(アンソニー・ホプキンス)からクラリス・スターリング(ジュリアン・ムーア)宛に送られてきた手紙の便箋にはかすかにハンドクリームの香りが残っていた。オーダーで作られたと思われるこの香りを調香師が分析し、それをヒントにクラリスはレクター博士の潜伏場所へと近づいて行く。いや、ときに鬱々とした表情を見せるフィレンツェの街で育ったリトアニア生まれのイタリア人、レクター博士がクラリスを呼び寄せるために仕組んだ「完璧な香り」と呼ぶほうが正確かもしれない。一時も目が離せないこのスリリングな映画を見ながら、ぼくは「アンバーグリス」という言葉に引っかかった。なんだこれ?どこかで聞いたことがある。
英和辞典でアンバーグリスをひいてみたら「龍涎香」(りゅうぜんこう)と訳されていた。龍涎香のことなら少しは知っている。「龍の涎(よだれ)の香」という漢字が当てられているが、想像上の生き物(神)である龍の涎ではない。調香師がいうようにクジラの腸内で生成される結石のようなものだ。しかもマッコウクジラの腸内でしかできない。それもきわめて稀にしかできない貴重なもので香料の原料になるという。
子どもの頃に愛読していた動物図鑑のクジラの項にそう書いてあった。その図鑑には「マッコウクジラは日本近海に生息する」とも書いてあり、日本の漁師によるマッコウクジラ漁の写真か挿絵が添えられていたという記憶がある。
【註記:映画『ハンニバル』には出てこないが、トマス・ハリスの原作にはレクター博士が400年続くサンタ・マリア・ノヴェッラ薬局のフィレンツェ本店で定期的に購入している記述があり、クラリスの自宅に宛てて石けんと香水を贈っていることが読み取れる。ちなみにサンタ・マリア・ノヴェッラ薬局は日本に支店を置いている。http://www.santamarianovella.jp/】
ナンタケット・スレイライド
クリームのプロデューサとしても知られるニューヨーク出身のベーシスト、フェリックス・パパラルディと、同じくニューヨーク出身の巨漢のギタリスト、レスリー・ウェストが結成したハードロック・バンド「マウンテン」の「ナンタケット・スレイライド」(1971年初出)を聴いたのは1972年、高校1年のときだったと思う。ナンタケットとは米国東部の港町で、かつてはアメリカにおける捕鯨の前線基地だった。この曲は、捕鯨船乗組員の悲運の物語(実話)を題材とした哀歌だが、レスリーの伝説的なハーモニクス奏法と情感たっぷりの唱法を堪能することができる作品として、マウンテンの代表作となっている(1972年の長尺ライブ・バージョンが特に秀逸)。
パパラルディと妻のゲイル・コリンズの共作だが、伝統的なブリティッシュ・フォークの要素とポップスの要素を織り交ぜた上、ハード・ロック的なサウンドで装飾した壮大な楽曲で、「ロック」という枠では捉えきれない奥行きを備えていた。ぼくのロック体験のなかでもっとも重要な楽曲の1つである。
【註記:パパラルディは1983年にゲイルに撃ち殺され(裁判所は過失致死と判断)、ゲイルは服役後行方をくらましたが、2013年にメキシコで変死体となって発見されている。なんとも凄い話だ】
『白鯨』の龍涎香
「ナンタケット・スレイライド」が大のお気に入りだったぼくは、この歌の題材となっている実話が、米国を代表する小説家であるハーマン・メルヴィルの代表作『白鯨』(1851年)の創作に影響を与えていることを知り、高校2年になってから飽きるほど長たらしいこの小説を読んだ。原題は“ Moby-Dick;or, The Whale”である。マッコウクジラ「モビィ・ディック」と捕鯨船ピークォド号のエイハブ船長との狂気の闘いが描かれている。
『白鯨』で再び龍涎香に出会った。
「そういうわけであるから、こよなく高貴な淑女や紳士は、病鯨の穢れはてた腸の中から取った香料を楽しんでいるのだ、とわれわれは考えざるを得ないが、まさにそうなのだから致方ない。人によっては、龍涎香(ママ。以下同じ)は鯨の消化不良の原因だといい、人によっては結果だという。いかにしてそのような消化不良を直すかといえば、むつかしい話であって、短艇三四隻に積みこんだブランドレスの丸薬を呑みこませてから、土工が岩石を爆破するときのように、生命からがら逃げ出してくるでもするより他はあるまい」
「ところで、このかぎりなく香わしい龍涎香の純粋なるものが、このような腐蝕の真只中に見出されるというのは、ふと したことであろうか。諸君は、『コリント書』中の聖ポオロの、腐敗と純潔とについての言を思い、人は汚辱のうちに投じられ光栄のうちによみがえる、ということを知るべきであろう。また同様にして、最高の麝香を生み出すものは何かというパラセルソスの言をも思うべきであろう。またあらゆる悪臭のものの中でも、製造の第一過程にあるコローン香水は最悪のものである、という奇異な事実を忘れるべきでなかろう」阿部知二訳『白鯨』(岩波文庫)「第92章 龍涎香」より
ここにもあるとおり、龍涎香は欧州の貴族やアメリカの金持ちのあいだでもてはやされるような珍品・逸品だった。エイハブ船長時代のマッコウクジラ漁は鯨油採取が主目的だったが、船乗りや漁師には「あわよくば龍涎香も!」という欲もあったろう。滅多にお目にかかれない希少なものだけに、龍涎香はきわめて高額で取引されていたからである(現在なら数千万円の価値があるといわれている)。
照屋林助の鯨糞
動物図鑑の龍涎香からマウンテンの「ナンタケット・スレイライド」を経て『白鯨』で再び龍涎香に出会うという若き日の偶然の連鎖は、これで終わりではなかった。次の舞台は沖縄だ。
ぼくは1991年頃から数年間、照屋林賢(りんけんバンド)の父君であり、博学の芸能家だった照屋林助の弟子のような立場にあった。沖縄を訪れるたびに林助の話(音楽史など歴史の話と民話)を聴き、各種講演会や座談会の鞄持ちを務め、楽器や機材の運搬を手伝い、夜は夜で飲み屋のハシゴに明け方まで付き合った。ベロベロに酔っ払うと「(沖縄)そばを食べましょね」といって24時間営業のゲーム喫茶に入り、麺をすすりながら汁に顔を突っこんで眠りこけてしまう巨漢の林助を背負い、100キロ近い体重に押し潰されそうになりながら自宅まで送り届けたことも何回かあった。
その林助がしばしば鯨糞の話をしてくれた。
「沖縄には昔から浜辺や磯を歩いて寄せ物(海の彼方から漂着物)を探す習慣があるが、貧しいウミンチュ(漁民)やハルサー(農民)にとって欠かせない習慣だった。というのは、ときに香料に使う鯨糞のような高価な物や外来の珍しい品が波に寄せられて浜や磯に打ち上げられるからである。こうした漂着物を役人に献上して幾ばくかのカネをもらう。税(貢祖や役務)を免除してもらうこともあったという。鯨糞は龍糞ともいわれていたが、人々は龍は見たことはないがクジラは見たことがある。だからクジラの糞だろうと考えていたようだ。意外と合理的だが、実際にはクジラの結石だったわけだ」
林助の話はざっとこんなものだったが、これはまさしく龍涎香のことだ。
歴史家の真栄平房昭の論稿「南蛮貿易とその時代」(『新琉球史 古琉球編』琉球新報社・1991年所収)には、龍涎香が琉球から日本への重要な輸出品目だったと記されている。江戸幕府の貿易品目を記録した『通航一覧』には、琉球から薩摩が輸入している品として龍涎香「17箱」「50袋」といった記載があるという。相当な量の龍涎香が獲れたと推測できる。薩摩だけではなく中国も琉球の輸出先だったから、『通航一覧』に記載されている以上の龍涎香が獲れたのかもしれない。龍涎香はマッコウクジラだからといって獲れるものではない。結石ができるクジラのほうがはるかに少ないからだ。したがって、かなりの数のマッコウクジラが沖縄近海に生息していたことになる。ところで、幕府は龍涎香をオランダにでも輸出していたのだろうか?そのあたりの事情はいずれ調べてみたい。
林賢が監督した映画『ティンク・ティンク』(1994年)のナレーションは林助が務めているが、冒頭部分で林助オリジナルの鯨糞(げいふん)の話が出てくる(ウチナーグチ/日本語字幕付)。軽妙な林助独特の語り口が心地よいこともあって、鯨糞はたんなる「一攫千金を狙えた海からの贈り物」ぐらいにしか思えないが、その背景には、人々の貧困があり、琉球王府と薩摩藩・江戸幕府の丁々発止のやり取りがあり、もっといえばエイハブ船長の時代の、あるいはそれ以前の時代の欧米支配階層とのつながりも見えてくる。博学の林助だから、そんなことは百も承知で「沖縄のちょっといい話」に仕立て上げているのかもしれない。
レクター博士がクラリスに仕掛けたアンバーグリスの甘い罠は、ひょっとしたら琉球の鯨糞がなければ成り立たないストーリーだったのかもしれない。これを歴史の偶然といったほうがいいのか、それとも歴史の必然といったほうがいいのかわからない。が、ぼくにとってマウンテン抜きで白鯨はなく、白鯨がなければ龍涎香に関心を持つこともなかった。さらに、照屋林助に出会わなければ鯨糞の話も知らなかった。そう考えると「偶然の連鎖は必然である」という命題が唯一正しいものに思えてくる。
3月10日は林助の命日である。林助ならこんなどうでもいい話を喜んで聞いてくれたことだろう。合掌。
なお、批評ドットコム(本サイト)には、照屋林助師の追悼記「照屋林助さんのこと」も掲載されている。2005年の『ミュージック・マガジン5月号』収録のテキストを再掲したものだ。併読をお奨めしたい。