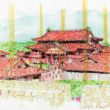沖縄県議選2024の分析:「オール沖縄」時代の終焉
「オール沖縄」時代の終焉?
沖縄県議選(2024年6月投開票/定数48)が終わった。「争点は、辺野古から南西諸島への自衛隊配備問題に移行」という地元メディアなどの論調が強かったが、篠原は、はなから玉城デニー知事の県政運営の行方を占う選挙でしかない、と考えていた。おまけに自衛隊が増強されている宮古八重山地方には、そもそも米軍基地がそもそも存在していない。基地問題がないのだから、「辺野古反対」といってもピンとくる住民は少なく、「国境の離島」だけに自衛隊を歓迎する住民も多い。現に石垣島区(定数2議席)では、無投票で自民候補・非自民候補が議席を分けあったし、宮古島区でも自民・公明・立民の3候補の争いとなり、自民党・公明党が議席を獲得している。いずれも「自衛隊」は争点にならなかったということだ。
「裏金問題」で岸田政権に対する逆風が強い段階での選挙だったから、県議選レベルとはいえ玉城知事の県政運営に批判的な自民党が議席を減らすと予想していたが、予想に反して、デニー県政を支える与党(オール沖縄系)のほうが24議席から20議席へと4議席減らした。他方、自民党は18議席から20議席へと2議席増、自民党に近い公明党が2議席増の4議席、日本維新の会が選挙前と変わらぬ2議席を維持し、自民系無所属が2議席(選挙前はゼロ)を確保するなど、非オール沖縄系野党が過半数を3議席上回る28議席を獲得して、県政レベルでの与野党逆転が事実上実現した。
円安と物価高騰が進行するなかで、岸田政権によって実質所得(実質賃金)の増加を計ろうとする政策が打ちだされているが、現状ではなんとも心許ない。多くの自治体で、それを補うべく地域的な所得再分配を実施しつつあるが、本来、自治体レベルでの所得再分配には限界がある。そうなると、住民あるいは国民は自治体の福祉政策・教育政策に期待する。沖縄県が検討したのは、義務教育段階での給食費の無償化、通学のためのバス料金に対する補助などだが、それは基地問題とはまるで関係ない施策である。与野党とも、福祉政策・教育政策あるいは少子化対策を強調したが、「オール沖縄」系与党は、デニー知事に右にならえするように「辺野古埋め立て反対・阻止」を公約に掲げていた。共産党候補者は、「辺野古反対」や「自衛隊増強反対」をとくに強調したが、そのせいもあって得票を大きく減らし、結果的に改選前7議席を3議席も減らして4議席に留まっている。同じオール沖縄系でも、「辺野古」や「自衛隊」ではなく「福祉政策の充実」を前面に出した候補者の大半は当選している。選挙に関心の高くない無党派層にとって、かつてのように「辺野古」はもはや心を動かす「魔法のことば」ではなくなっている。これはきわめて重要な変化で、「辺野古」に直結して結束を保っていた「オール沖縄」にもはや実体はないのではないか。
つかみにくい県民の民意
議席数ではなく、得票状況から県全体の全体の民意の動向を推し量るのはきわめて難しい作業である。国政レベルにつなげて論じるには、自民、立憲民主、公明、維新、共産などの主要政党が並び立って競う必要があるが、そした条件を満たすのは那覇市・南部離島区のみで、他の選挙区ではほぼ見られない。しかも、オール沖縄系は無所属の候補が多いのが特徴で、今回は全県で12人が立って9人が当選しているが(改選前は10議席)、無所属候補の属性や個々の主張を平準化するのは困難である。沖縄の場合、地縁血縁が投票行動の動機になっているケースが多く、政党公認の候補でさえ少なからず地縁血縁に支えられている。無所属となると人格的要素に地縁と血縁が入り込み、さらに複数の推薦政党の主張が上塗りされているので、実につかみどころがない。以上のような理由で、ここでは那覇市・南部離島区の得票の推移を手がかりに民意の動向を探ってみたい。
那覇市・南部離島区にみる投票率・有効得票数の推移
那覇市・南部離島区(以下那覇市区と略す)の場合、定数11に対して、今回(2024年)は19人、前回(2020年)は16人、前々回(2016年)は18人が立って得票を争った。投票率は、それぞれ43.88%、44.72%、、52.11%、有効得票総数は同じく112,617票、116,314票、132,781票であり、投票率、得票総数とも減少傾向にある。被選挙権年齢は2016年6月19日より引き下げられた。したがって、同年6月5日に実施された前々回選挙の時点で18歳、19歳の市民は投票できなかったが、投票率・有効得票数とも直近3回の選挙では一番高い数値を示している。
これを党派別に見ると、以下のような状況となっている。
3回の選挙を通じて読み取れるのは以下の点である。
- 2024年と2016年を比較すると、自民党の得票数はほとんど変化がない。
- 同じ期間の社民党の得票数は三分の一近くまで後退している。
- 同じ期間の共産党の得票数は3割減である。
- 公明党の場合、2020年の選挙で候補者をふたりからひとりに減らしたため(コロナによる選挙運動の縮小が理由)参考にできない点もあるが、得票は17,000〜18,000票と安定的に推移している。
- 社大党(地域政党・社会大衆党)は、共闘・協力する友党・社民党に比べて安定した得票を得ている(全県では1議席から3議席へと躍進)。
- 立憲民主党の場合、沖縄県では政党支部組織が固まっていないため、候補者数の変化(2020年1名、24年2名)に左右されている。
- 知事派(オール沖縄系)の得票数と非知事派(反オール沖縄系)の得票数は、2016年〜24年の間、完全に逆転している。
- 城間幹子市長の引退を受けて実施された2022年の那覇市長選では、自公両党の推薦で出馬した知念覚氏(前副市長)が 64,165票を得て、54,125票を得た翁長雄治氏(翁長雄志前県知事の子息・前県議/立憲・共産・社民・社大・れいわなどオール沖縄系政党が推薦)を下したが、 今回の県議選で非オール沖縄(非知事派)側が得た得票は知念氏の得票とほぼ同数である。
- 市長選時と変わったのは、オール沖縄(知事派)側がさらに6000票ほど減らしているという点である。
- 那覇市区についていえば「オール沖縄」はほぼ消滅している。すなわち。「オール沖縄」は保守派・中間層・無党派層の一部を取りこんで成立してきたが、もはやその構図は描けないということがはっきりした。
ポスト「オール沖縄」時代の到来〜より健全な政治と社会の実現
「オール沖縄の終焉」を全県にまで敷衍して考えられるかについてはまだ検討の余地があるが、「辺野古」や「基地反対運動」はもはや沖縄の政治や社会を語る上でのキーワードではなくなっていることは明白だ。それに代わって何が政治課題として浮上するかといえば、「貧困=所得再分配」や「補助金依存体質」の改善など、県民生活の安全・安定を実現するための諸施策である。
その意味では、沖縄県の自治はより健全な方向に向かいつつあると判断できるが、「誰かが何かをやらかす」ことによってこの流れは簡単に覆されてしまう可能性はある。それが政治家や企業に起因する事態なのか、それとも米軍や自衛隊に起因する事態なのか、あるいはそれ以外の外的要因に起因する事態なのかはなんともいえないが、少なくとも政治家・官僚・企業・個人は不測の事態に備えて、自らの危機管理意識をより高めていく必要があると思う。