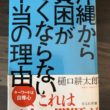米価高騰の真犯人は農水省とJA(農協)— 望まれる「既得権重視」農政の転換
備蓄米の放出が始まったにもかかわらず、お米の値段が高止まりしている。いや、それどころか、店頭の小売価格は5キロ4500円程度と昨年夏以前の価格の2倍近く、先週よりも今週の方が値上がりしている。
市場原理に照らすと、備蓄米21万トンの放出分が消費市場まで適切に届けば米価は間違いなく下がるはずだが、そうはならないのがとても不思議である。「卸売段階や消費者段階での買いだめが米価高騰の原因」という農水省の説明がおかしいとしか思えない。
いろいろ探してみても、「農水省の説明のおかしさ」を指摘するテキストは少なかったが、元農水省のキャリア官僚で、キャノングローバル戦略研究所研究主幹の山下一仁氏のふたつの論説を読んでようやく納得した(論説1および論説2)。
山下氏は、
- 1.2023年の米の収穫量は「平年以上(作況指数101)」とされたが、猛暑の影響で粒の揃ったコメ(整粒)の比率が低下し、玄米から精米にしたときの歩留まり率も低下した。その結果、小売り段階の供給量は、作況指数で測られる農家段階の玄米のときより減少し、20〜30万トンの供給が減ったと推計される(主食用米の総生産量は660万トン)。
- 2.この減少分を、2024年産の米で補ったために(いわゆる「先食い」)、2024年夏以降の米価の高騰を招いた。
- 3.したがって高騰の原因は、農水省が説明するような「投機目的の卸業者による買いだめ」などではなく、2023年の実質的な「不作」にある。
- 4.農水省は、2018年に指向した「トレーサビリティ法」(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)により米の流通経路は把握しているから、高騰の原因が卸売業者の投機目的にないことなどわかっているはずだが、農水省自身や農協(JA)などの既得権益を守るために嘘をついている。
と主張している。
JAの既得権益については、TPPが話題になった頃からたびたび批判されているが、与野党の政治家は「農業票」欲しさに、JAを表だって批判することはない。
「令和の米騒動」の元凶はJAとJAの既得権を守るように構築されている農政のあり方だ。マスコミや識者はそれを知ってか知らずか、農水省の口車に乗って、「投機的な卸売業者」に責任を転嫁している。マスコミと識者のこの偏った姿勢を指摘する声は少ないが、やはりその責任は重大だと思う。
考えてみたら、「投機目的」で米という現物(米は「準生もの」である)を隠し持つことなどできない相談で、端から農水省とJAを疑うべきだったのだ。市場原理と乖離した農政のあり方はやはり徹底して問われるべきだと思う。
批評.COM 篠原章