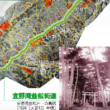【特集: はっぴいえんど】サエキけんぞう×篠原章対談 第2回
Saeki Kenzo & Shinohara Akira ; Talk About Happy End, the Japanese Most Legendary Rock Band Vol.2
サエキけんぞう×篠原章対談 第1回からつづき
特集: はっぴいえんど
サエキけんぞう×篠原章対談 第2回
サエキけんぞう×篠原章対談 第2回!
傑作『はっぴいえんど』(ゆでめん)の底知れぬ暗さはどこからやってきたのか?
サエキけんぞう
「今日、聴きたいことがあって、それは『ゆでめん』の持つ“暗さ”についてなんですよ。」
篠原章
「凄くいいポイントだと思います。もともとはっぴいえんどは、細野さんと松本さんのバンドですが、60年代末的な、ある種の世紀末的な暗さを引き摺りながらスタートしたんだと思います。これには、冷戦やベトナム戦争を主な理由として60年代アメリカン・ドリームが崩壊してしまったことも関係があります。目標とすべきカルチャーのモデルがなくなったような状態ですからね。が、松本さんは、早々突破口を見つけたんですね。『ガロ』とかの世界もありますが、詩人で建築家の渡辺武信さんなどの影響もあって、新しい時代の都市論あるいは日本語表現にたどりつきつつあった。松本さんは言葉の人でもあったから。」
サエキ
「それは、わかります。」
篠原
「ところが、根っからの音楽人である細野さんは、はっぴいえんど結成の頃、まだその突破口を見つけられていなかったんだと思います。アメリカとイギリスのあいだで彷徨うような状態というべきか。“楽しいポップス”がなくなり、深夜に黙りこくって一人で聴くようなロックも台頭してきたなかで、自分はどうふるまうべきかという壁にぶち当たってた。はっぴいえんどは、その壁を壊す舞台として用意されたんだと思いますが、なんと細野さんよりも先に大瀧さんのが開眼してしまうんです。それが<12月の雨の日>とか<春よ来い>に結実してるわけです。ぼくは細野さんの『ゆでめん』の曲も大好きなんですけど、大瀧さんのこの2曲は、時代に風穴を開けるような迫力があった。一方の細野さんはまだ焦燥感を抱えたままで、そこからなかなか前に進めないって状態だったんじゃないでしょうか。それが『ゆでめん』の持つ暗さの一因だと思います。じゃあ、大瀧さんはどうだったかというと、<12月の雨の日>とか<春よ来い>とか いった傑作をつくってもなお、はっぴいえんどの中での居場所を探すような状態だったんじゃないでしょうか。岩手から出て来て、東京のど真ん中で生まれたようなバンドに入ってちゃったわけですから、その孤立感は今ぼくたちが想像する以上に大きかったんだと思います。大瀧さんのこの孤立感も、はっぴいえんどが 成功する原動力のひとつになったわけですが、大瀧さん自身はその孤立感をもてあましていたんだと思います。大瀧さんのこの孤立感も『ゆでめん』の持つ暗さ の一因だと思います。」
サエキ
「「12月の雨の日」の暗さは、まさに、そこを代表していて、あれを聴くと僕は、雨の日の新宿西口の外出たと」ころの人の流れを思い出します。今でも雨の日に新宿に行けば感じる。とにかく湿ってて、暗い。」
篠原
「ぼくはなぜか赤坂見附だったんですけど(笑)」
サエキ
「赤坂見附って、人が流れてますか?」
篠原
「東急ホテルのある赤坂東急プラザから見る赤坂見附ですけど。」
サエキ
「あそこも昔の匂いのする東京ですね〜。1970年当時、時代が大きく変わろうとしていて、そこに盲目的に人が流れる感じを新宿に感じました。今の世相と、ちょっと似ているところがある。」
篠原
「赤坂東急プラザから見ると、赤坂見附の人の流れがとてもよく見えるんです。たぶん今でも。歩道橋を人が流れていく。ま、それはそれとして、『ゆでめん』の暗さを理解するポイントは、大瀧さんの孤立感と細野さんの焦燥感なんだと思います。」
サエキ
「大滝さんの孤立感、岩手を出てこられて東京で暮らしていた大滝さんの孤立感は切り立っている。エッジにいた細野さんの焦燥感、それは時代に対して何とかしなくてはならないという焦り。そこが際立つポイントですね。」
篠原
「松本さんが何かのインタビューで語っておられたけど、大瀧さんという岩手出身の人を入れることで、フォークの世界のカントリーっぽいパワーを、東京のバンドであるはっぴいえんどに導入できるんじゃないかと考えたって。大瀧さんを入れたのは、松本さんにとってちょっとした戦略だったってことですよね。 大瀧さんは、それを覚悟した上であのバンドに入ったんですよ。」
サエキ
「音楽の問題というより、人間としてどういう人間と組むか?ということでしょうか?」
篠原
「松本さんにも、明治から昭和という歴史のなかで育まれた東京の文化に対する何らかのコンプレックスがあったのかもしれませんね。どこか斜めに見ているみたいな。逆にいえば、松本さんは、東京を客観的に見られる立場だったんでしょう。その意味で、鹿鳴館文化に通ずる、あるいは欧米カルチャーに対して開かれた、明治以降の東京の文化的伝統を体現できる立場にあったのは細野さんだけだったんです。東京文化のコアにある希有な人なんですよ、細野さんて。」
サエキ
「なるほどね……。」
篠原
「細野さんという、いってみれば東京文化のエスタブリッシュメントの側にいる人に松本さんが絡んだのは、意識的・無意識的に、東京文化の伝統性みたいなものに接近したかった、ということもがあるんじゃないかと思います。”東京”そのものを代表できるのは細野さんだけですから。」
サエキ
「今では見えにくくなった、文化の階層についての所見ですね。」
篠原
「でも、その細野さんも自分の役割を知って身動きがとれないという焦燥感があったんでしょうね。さっき話したように、先日、パリで細野さんの同級生に会ったんです、偶然。パリに30年住む日本人の男性。大学は立教の観光学科で、細野さんと完全に同級。“細野君は全然学校に出てこないから親しくはなれなかったけど、周囲が心配になるほど暗かった”と仰ってました。」
サエキ
「その感じ気になりますよ。暗いっていうのが。」
篠原
「エイプリルフールのアルバムを出したときはものすごい長髪になっていて、“今度、ぼくアルバム出したんだ”とぼそぼそ語っていたそうです。」
サエキ
「音楽的に合理化して分析すれば、1968年頃のサイケデリックなニューロック的な盛り上がりって、完全に輸入文化で、リアルタイムにはマネしようがな かった。GSはGSというフォーマットでやるしかなかったし、ゴールデンカップスはブルースロックだった。ジミヘンやクリームニューロック的なサウンドは、1968年には実現不能だった。それが1969年になると変わってくる。とはいえ、様々な技術がまだまだでした。だから、その暗い感じ、凄くわかります。1969年のエイプリルフールのアルバム、いいですが、暗いです。もしあのまま、はっぴいえんどがなければ?細野さんは暗いままだったのでしょう か。」
篠原
「どうでしょうかねえ。ここでいえることは、はっぴいえんどの暗さは、エイプリル時代から引き摺っているサウンド的な暗さ、大瀧さんの孤独感、細野さんの焦燥感が、入り交じっているってことですね。」
サエキ
「僕は、そこに技術問題以前というか、技術とは関係ない、当時の日本の若者の必然的な暗さも感じてしまう。」
篠原
「そこはもう少し掘り下げられるかもと思います。」
サエキ
「お互いのライバル心も、そうした「暗さ」を背景にしたものだと思うのですが?いかがでしょうか?『ガロ』も暗かった。『COM』も暗かった。でもGSは明るかったし、テレビつけたら、かなり面白かった。『ゲバゲバ90分』とか。」
篠原
「あの時代の東京の若者一般って、実はそれほど暗くなかったんじゃないか、という思いもあります。ロックや芝居やっている人たちには、なにか象徴的に暗い感じがあるけど。」
サエキ
「今回のはっぴいえんどのボックスセット『はっぴいえんどマスターピース』に松本さんの当時の詞を記したノートが付いていて、そこにこんな一文があるんです。
“青春は限りなく痛む傷痕の陰に立ちすくんでいる 都市の抒情を唱う彼ら はっぴいえんどはきっと ぼくらの傷口に やさしい風を 吹き込んでくれるだろう”
と、青春の傷について明確に触れているんですね。だから「ゆでめん」は、大滝さんの係わる、唯一、暗い盤ですね。あとはポップスの明るさがイメージを明るくしてる。」
篠原
「初期のはっぴいえんどといえば、<春よ来い>であり<12月の雨の日>、あるいは<かくれんぼ>。」
サエキ
「<飛べない空>という曲があるじゃないですか。これが象徴している暗い世界がある。」
篠原
「アレ傑作ですよ。でも、ライブでやったことはないんじゃないでしょうか。」
サエキ
“閉ざされた陸のようなこころに 何が起こるのか”
「まさに自殺しそうな人の歌。これに“お正月といえば・・・何処で間違えたのか?”という詞が重なると、かなり暗い!」
篠原
「<飛べない空>は細野さんの詞曲で、松本さんの創りあげようとした世界に細野さんが乗り切れなかったことを象徴するような楽曲ですね。」
サエキ
「そうです。だから自殺しそう。『ゆでめん』の演出について、詳しくお聴かせください。」
篠原
「松本さんの世界は、もうかなり出来上がっているんです。あの段階で。それを音楽としてどう表現するかってことが細野さんと大瀧さんの課題だった。お そらく細野さんには、松本さんの詩の世界を音として表現し切れないっていう焦燥感があって、それが暗さの背景にあるんだと思います。ところが、大瀧さんは意外にも素直に表現出来ちゃったんです。それがますます細野さんの焦燥感を深めたんじゃないでしょうか。」
サエキ
「大滝さんは作曲家志望だったといいます。ですから、詞を曲にするということでは、一歩先んじておられたのかもしれませんね。松本さんの演出・・・?『ゆでめん』の松本さんの詞世界は、後に比べると、圧倒的に暗い。“曇った空の浅い夕暮れ”(『かくれんぼ』)“古惚け黄蝕んだ心は 汚れた雪のうえに落ちて 道の端の雪と混じる”(『しんしんしん』)写実もメチャクチャ暗い(笑)。」
篠原
「まあ、そこはけっこう中原中也的な暗さですね。でも、ちょっとした演出とか戦術もあると思います。当時、松本さんが参考にしていた遠藤賢司さんなんかの“フォーク”も暗かったし。が、そんな中で切磋琢磨があって。細野さんの<敵タナトス>って曲。あれは松本さんの作詞ですが、じっくり聴くと<はいからはくち>の元歌じゃないかとも思えます。SEの入れ方とかも。」
サエキ
「最後のドラムのドンチャカが、<はいからはくち>のドラムソロと酷似してます。」
篠原
「そうなんです。細野さんがいたからこそ大瀧さんがあの曲を作れた。暗さの切磋琢磨ですね。いってみれば(笑)」
サエキ
「“何を怨うか 何を呪うか”(タナトス) もう使っている言葉が圧倒的に暗い!これが『風街ろまん』では、“空色のくれよんで君を描いた”になる。これは物凄いカーヴじゃないっすかね〜。」
篠原
「新しい突破口を見つけたんですね。」
サエキ
「そのカーヴこそがはっぴいえんどの描いた壮大なドラマで。でも子供だったけど、『風街ろまん』的な風情は、マックスロードとか、たんまり共有できました。しかし、『ゆでめん』は・・・。」
篠原
「『ゆでめん』が出た頃は、もうローラ・ニーロの世界とかにいっちゃてるんですよね。カントリー的な素養もみな身につけ始めていたんだと思います。70年の後半は。自分たちが本来好きだったポップスに近づいているっていう感じはあったんだと思います。」
サエキ
「僕がはっぴいえんどを知ったのは、さっき通りかかったジャックスファンクラブの清水さん。お姉ちゃん」
篠原
「パリで会った細野さんの同級生もジャックスファンクラブ。」
サエキ
「はっぴいえんどはジャックスとつながってた。ジャックスの暗さを考えると、『ゆでめん』の暗さも理解の糸口にはなる。先ほどの清水さんも『ゆでめん』と ジャックスは同じような気持ちで聴いてたといってた。早川さんのあの暗黒を描くような意図は、その後、アーティストとしは誰に継承されたのでしょうか。」
篠原
「時代的な暗さっていうことがいいたいのでしょうか?」
サエキ
「それがですね、小学生だったから、全くわからないのです。」
篠原
「ほんとうの暗さとはチョット違う気がするんだよなあ。」
サエキ
「たとえば、細野さんが周囲が心配するほど暗く見えたとして、それは何故だったのでしょう?品格のある家にそだち、沢山の文化を追求しながら、どうして暗かったんでしょう。」
篠原
「沢山の文化を吸収しているから、暗かったんじゃないでしょうか。これは俺の文化だろうか?っていう自問自答が続いたんだと思います。」
サエキ
「それは何となくわかる。」
篠原
「あがた森魚さんは、時代を1964年で区切ってるんです。」
サエキ
「ビートルズ?」
篠原
「ディラン以前とディラン以後。64年まではポップスは楽しかった。65年から使命感に変わったって。”表現”ってことを気にしだしたんだと思います。あがたさんの場合、ディランを聴いて、ポップスの享受者じゃなくて発信者になろうと思ったんでしょうね。」
サエキ
「大滝さんのお考えにも近いですね。ポップス以前に回帰された大滝さんと。ボーイミーツガールを歌い、気楽な娯楽だったポップスに、ロックの影響で様々な表現の可能性ができ、そこが楽しさを奪った面があった。」
篠原
「今回のあがた森魚さんの新作『浦島64』は窪田晴男サウンド・プロデュース、なんだけど、その時代の気分を窪田君に伝えるのは大変だったと。」
サエキ
「おお、そうなんですか!僕の考えてることにもストライク!です。」
篠原
「この作品、あがたさんの歴史に残る名盤ですよ。窪田さん抜きではできなかったけど。」
サエキ
「まさに、僕が話したいことだし、知りたいことでもある。」
篠原
「71年頃のあがたさんの詩集=ガリ版刷りに、“今日、北大に機動隊が導入されて惨憺たる気分になった”という表現があるんですが、社会的・政治的な流れのなかで、自分が表現者としてすべきことはどこにあるのか、という自問自答があるんですね。あの頃は。」
サエキ
「それは本当にユウウツだと思う。学校に権力が入るのは、イヤになるでしょ。表現の自問自答という状況も、気分がわかってきました。」
篠原
「実は、今思えば大したことじゃないんです。ほんとうは。学生運動は、機動隊と対決してナンボの世界でしたから、肉体的なぶつかり合いのなかで、自己実現していたんだと思います。」
サエキ
「僕はデモは、街角などで割とみたので、すべて曇りの風景として記憶してる。太陽の下の感じじゃなかったです。」
篠原
「うーん。それは(サエキの兄弟の)真一さんにきいたほうがいいけど、あれはフェスティバルとかスポーツ大会に近い世界でしたよ。あの頃の学生運動にはなんともいえない高揚感がある。逮捕されても誰も問題にしない時代で、実は就職にさえひびかない。」
サエキ
「いや、そんなことは断じてないです。暗いですよ。学生運動している姉兄とかいると、家の中が凄く暗かったの。当時、佐伯家は。」
篠原
「それは真面目だったからです。」
サエキ
「そういう人も沢山いたんですよ。断言しますが、権力との対峙は、非常に消耗するものだと思います。水俣しかり、原発しかり、安保しかりです。政治の運動があるとして、その中核には、ラグジャリーとは遠い意志がなければ、成立しません。」
篠原
「真面目な人もいたけど、中核とか、ぼくは体育会系の人とあまりちがわないって思ってました。」
サエキ
「僕の認識は、屈折と、変節でした。あの70年代初頭の時代の変遷と受けとめきれず、自殺に至った人も多いはず。『ノルウェーの森』にもありますね。気分の変化として“お祭りみたいだった”お話しとか、いまいちピンと来ません。」
篠原
「要するに彼らは、ジグザグデモやゲバ棒で、権力の象徴である警察と対決して楽しんでたと思います。卒業生の大半は企業に就職するわけですからね。」
サエキ「警察との対決は、お世辞にも楽しいとはいえないと、子供でもわかりました。権力側は、常にギミックを用意するからです。運動をした学校にいて、その認識がないというのは、ちょっと驚きます。そこを意識した文学も多いですが、共感したのは、高橋和巳とかですね。『我が心は石にあらず』とかメチャくらいですね」
篠原
「暗いもの、いっぱいありますよ。ほかにも。でも、見かけ上の暗さと本質的な暗さはやっぱり違うんだと思います。あの時代の暗さってのは、新しいのものを 生みだせるか否かっていう不安がない交ぜになった暗さで、実はけっこう前向きだったんじゃないでしょうか。ま、ここは立っていた場所によって認識の違いが出ちゃうかもしれないけど。」
サエキ
「良くわかりました。もちろん時代は多面性がありますし、とらえ方は色々ですから。」
追記:サエキけんぞう
サエキけんぞう×篠原章対談 第3回につづく
全6回
サエキけんぞう×篠原章対談 第1回
サエキけんぞう×篠原章対談 第2回
サエキけんぞう×篠原章対談 第3回
サエキけんぞう×篠原章対談 第4回
サエキけんぞう×篠原章対談 第5回
サエキけんぞう×篠原章対談 第6回(最終回)

はっぴいえんどのデビュー・アルバム『はっぴいえんど』(通称「ゆでめん」)