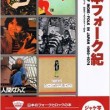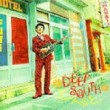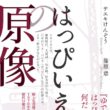坂本龍一と毛沢東
ぼくにとっての坂本龍一の最高傑作は、最初のソロアルバム『千のナイフ』(1978年)だ。
初回プレスは500枚。そのうち売れたのはわずか200枚だったというが(布谷文夫『悲しき夏バテ』に匹敵する)、当時はそんなことも露知らず、ぼくは発売当日に買っている。1975年前後のティン・パン・アレー(細野晴臣・鈴木茂・松任谷正隆・林立夫)のツアーのセッション・メンバーだったからだ。腰まであるような長髪に雪駄ばき、という異様な風体でキーボードを叩くその姿は、いまでも記憶に深く刻まれている。
もっとも印象的なのは、タイトル曲の「千のナイフ」とラストの「THE END OF ASIA」。2曲とも、毛沢東思想が曲想の原点にあるが、「千のナイフ」では、当時はまだ珍しかったヴォコーダーを使って、毛沢東の1965年頃に創られた詩篇「ふたたび井岡山(いこうざん)に上る」が朗読されている。
「なんで毛沢東?」と疑問を持つ人も多いだろうが、1970年前後に学生運動にかかわった者にとって、毛沢東と、毛沢東の復権を狙って中国各地で猛威を振るった紅衛兵は特別の意味があった。とくにフランスと日本では。
ハナタレ中学生だったぼくも紅衛兵に焦がれ、LT貿易(まだ国交のなかった中国との特殊な貿易方式)に従事していた伯父から中国土産でもらった毛沢東バッジ(当時、中国土産といえばそんなものしかなかった)を詰め襟の胸につけて学校に通い、毛信仰のきっかけを作った、林彪の選になる『毛語録』とマルクスの『共産党宣言』を常時携帯していた。「日本でも紅衛兵に倣い、自分たちのような十代の若者が主導して明日には自民党政権を転覆して共産主義政権を打ち立てる。アメリカ帝国主義を打倒してベトナム戦争を阻止できる!」と本気で信じていた。
ぼくの場合、「革命の野望は愚かな幻想にすぎない」と気づくのに時間はかからなかったが、70年代前半までは、毛沢東思想を「信仰」する学生(高校生・大学生)は山ほどいたと思う。
坂本龍一もそんな学生のひとりで、ぼくよりも年輩で、ぼくよりも真面目だったのだろう、おそらく『毛沢東選集』を熱心に熟読し、70年代後半になっても毛沢東に強い敬意を抱いていたに違いない。
だが、細野晴臣、高橋幸宏、松武秀樹が協力して創った『千のナイフ』のサウンドは、「毛沢東思想」を蹴散らすぐらいのとんでもないパワーがあった。坂本にとってそれは想定外だったかもしれないが、『千のナイフ』の直後に結成されたYMOの楽曲に、毛沢東の影は一切感じられない。
YMOは「赤い人民服」を纏って登場して人々を驚かせたが、毛沢東思想の洗礼を受けなかった細野と高橋にとって、この「赤い人民服」はたんなるパロディに過ぎなかった。が、ひょっとしたら坂本にとってはパロディ以上の意味があったのかもしれない。
参考までに、坂本が引用した毛沢東の詩「ふたたび井岡山に登る」の和訳を貼りつけておく。
原題「水調歌頭・重上井岡山」(ふたたび井岡山に登る)
つとに雲を凌ぐ志を抱きて ふたたび井岡山に登る
千里を旅して縁の地を訪ね 懐かしい面影に出会う
旧きかたちは 新しき姿に変わりぬ
至るところに 鴬が歌い 燕が舞う
水のせせらぎありて 高き路 雲の端に入る
光り輝く海を過ぎれば 険しきところ見るまでもなし
風雷轟き 戦旗はためく これぞ人の世
三十八年過ぎ去りしが それは一瞬のこと
天に上りて 九天の月を抱き
五洋に潜りて 鼈(べつ)を捕う
笑いさざめきて 凱歌を挙げて還る
世に難きことなし 攀援(はんえん/よじのぼる)の志あれば
(参考:人民中国インターネット版)
批評.COM 篠原章